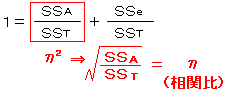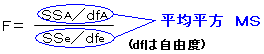パラメトリックな検定−分散分析
| ・分散分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | F分布を利用して分散の比の検定を行うもので、等分散性の検定に用いられる。 分散3群以上の平均値の比較の際に用いられる分析。 (1)正規分布であること、(2)誤差分散の等質性があること、(3)外れ値、異常値がないこと、の3つの大前提がある。 分散分析は分散の分解である。 基本モデル(データ構造)は以下の通り。
[1要因の分散分析表]
2要因の場合、主効果と交互作用の検定をする。 つまり SST=SSA+SSB+SSA・B+SSe を検定することになる。 F検定は1要因と同様にして行う。 [分散分析のフローチャート]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | ・多重比較 | |
| ■ | 分散分析で有意差の見られた要因について、さらにどの水準間に有意差があるのかを調べるために用いる。 | |
| ■■ | ・先験的比較(事前比較) | |
| ■ | 比較したい平均値の対が実験前に指定されている場合の方法。 たとえば、統制条件と他の水準との効果の相違だけに関心があるときに用いる。 Dunn法やDunnett法などがある。 | |
| ■■ | ・事後比較 | |
| ■ | 前もって特定の水準間の差に関心があるわけではなく、主効果が有意のとき、有意差が認められる水準すべてを検出したいときに用いる。 事後比較の方法には、Tukey法(HSD法)、LSD法、Duncan法、Student-Newman-Keuls法、Scheffe法、Ryan法などがある。 検定力は低いが頑健性が高いScheffe法がよく用いられる。 | |
| ■ | ・交互作用 | |
| ■ | 2因子以上の分散分析において、1つの因子の水準の違いによる観測値の間の差が他の因子の水準の影響を受けないとき交互作用がないといわれ、 その差が他の因子の水準によって有意に異なるとき、2つの因子の間に交互作用があるといわれる。 | |
| ■■ | cf.適性処遇交互作用(ATI) | |
| ■ | さまざまな適性の人々が環境から異なる処遇を与えられたとき、その処遇による結果がその人の適性だけからも説明されず、 両者の組み合わせによる独特の効果を示すとき、これを適性処遇交互作用という。 教育場面などでは、教授効果の有無を考える際に、被験者(生徒)の適性を考慮に入れる必要があることがしばしばあり、 そのため単に特定の教授法の優劣のみを論じるのではなく、生徒とのマッチングをも視野に入れる必要がある。 それゆえ、この交互作用が有意かどうかを常に考慮しないといけない。 | |